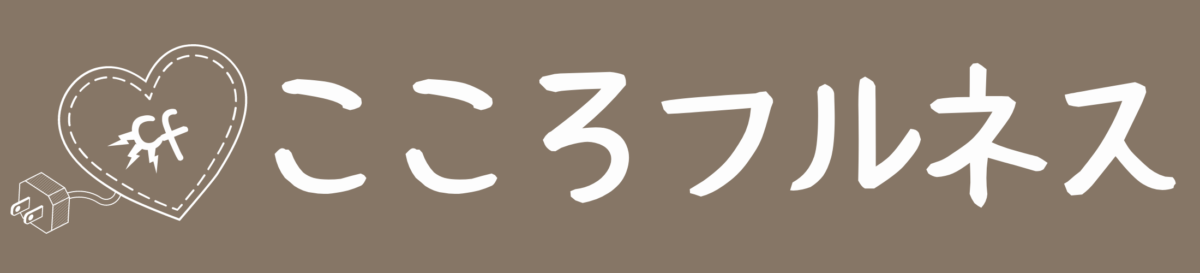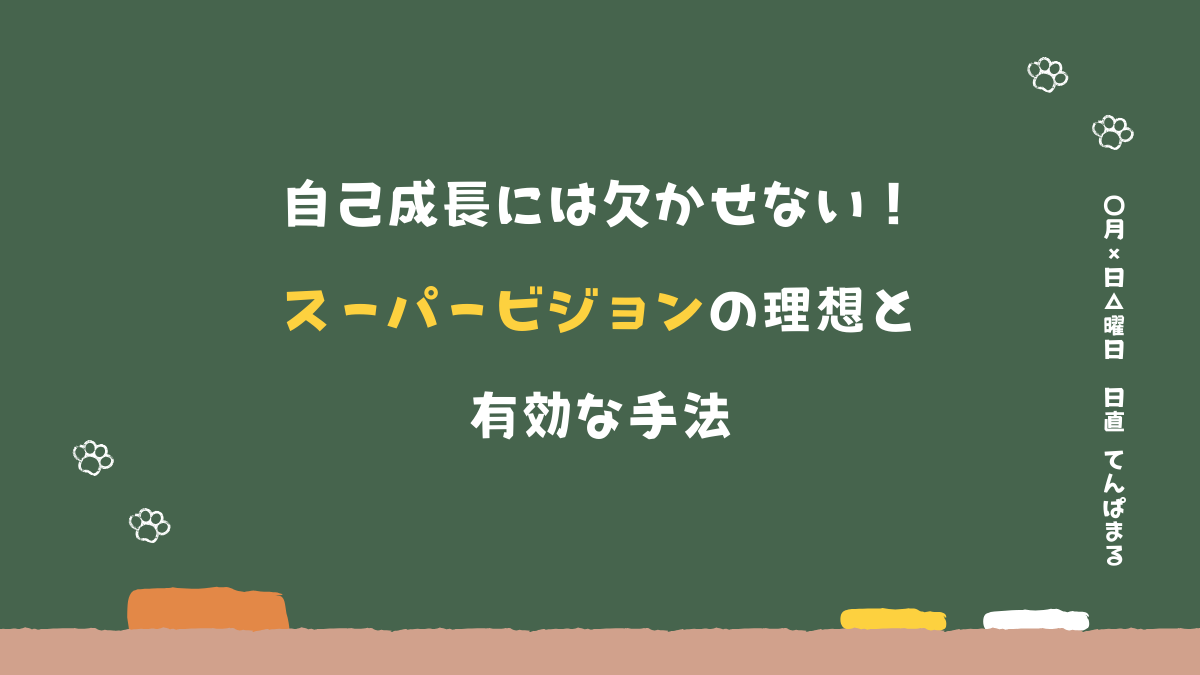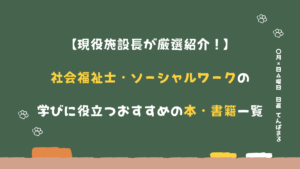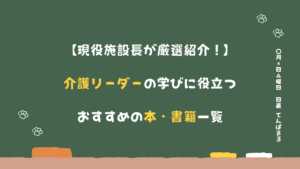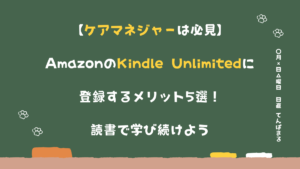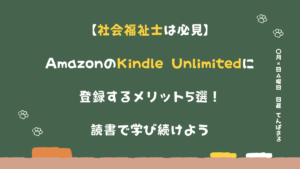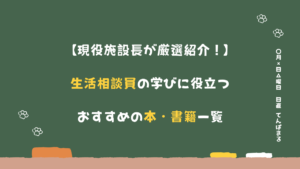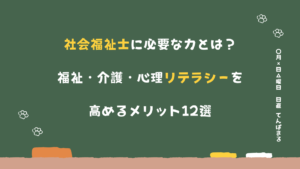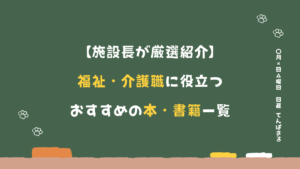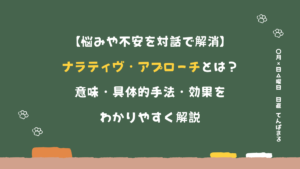スーパービジョンの重要性は従来から多くの実践家・研究者が指摘し、近年ではケアマネジャーの成長においても注目度が高まっています。
主任介護支援専門員の研修においてもスーパービジョンを学びますが、スーパーバイズの概念を学ぶことはできても、スーパービジョンのスキルを十分に習得できるまでの時間は確保されていません。
法廷研修のみをもってスーパーバイザー(以下バイザー)を要請することは、不可能に近いとも感じられます。
しかしスーパービジョンは、ケアマネジャーをはじめとした対人援助職にとって、「自分の知識・スキルの基盤をそれぞれ固有の環境・特性をもつクライエントに合わせて応用できる有効な手法」であることは明白です
つまりスーパービジョンの質を高めることが、「対人援助職のエキスパートに成長するための最も効果的な手法」と言っても過言ではありません。
この記事では、「現実的かつ本質を見失わないスーパービジョンはどうしたら展開できるのか」について詳しくお伝えしていきます。
最後までご覧ください。
スーパービジョンの理想
スーパービジョンの経験がある人もない人も、「スーパービジョンとはどのようなものなのだろうか?」と考えながら、以下のエピソードを読んでみましょう。
Aさんは大学でソーシャルワークを学習した後、人材育成に力を入れている高齢者施設を就職先に選択し、相談業務に携わるようになりました。
就職後すぐにバイザーと呼ばれるBさんが指導者となりました。
Bさんは相談業務10年のベテランです。
職場の方針でBさんは「毎週1回1時間」の頻度で、スーパービジョンの時間をとってくれることになりました。
スーパービジョンの準備として、AさんとBさんの間では「スーパービジョンの実施方法」に関する以下の6点を取り決めました。
- スーパービジョンで話し合ったことは、スーパーバイジー(以下バイジー)であるAさんの承諾を得ない限り、他者へ話すことはなく秘密として守られる
- スーパービジョンでは、バイジーが「自ら考え、自分の今後の方針を考える」という主体的な姿勢を前提にする
- バイザーはAさんの知識・スキルのレベルを確認し、レベルに応じて最適な教え方を活用する
※たとえば「情報提供やアセスメント情報の理解を深めるための問いかけ」でバイジーの思考を促したり、ロールプレイなどを実施する - バイジーはバイザーとの間で取り決めした様式に従った「記録」を持参する
※複数の担当ケースの「要約報告記録」とともに、1つのケースを決めて、面接でのやりとえいをできる限り思い出し、その内容を記録したものを書き、「自分自身が気づいた支援アプローチの課題」もできる範囲でよいので考えてくる
※この記録は相談機関に残す正式な記録ではなく、バイザーとバイジーの間のみで共有されるものである - 担当ケースが深刻な問題に発展しそうであったり、すぐに何かの情報が必要だったりする際には、定期的なスーパービジョンとは別に、その時々でバイザーのアドバイスを求めても良い
- スーパービジョン実施期間や目的を取り決め、終了時点でお互いに「何が達成できたか」「何ができなかったか」を振り返る
バイザーのBさんはバイジーのAさんの反応に常に注意を払いつつフィードバックを求め、理解できたかどうかを確認することを忘れずにスーパービジョンを行いました。
いかがでしょうか?
このエピソードを読んで「わたしもこれに近いようなスーパービジョンを受けていた」と感じた方は、非常に恵まれた環境にあると言えます。
実際のところ「こんな素晴らしい職場はどこにあるのだろうか?」と感じた方が多いのではないでしょうか。
このエピソードはあくまでも「スーパービジョンの理想の形」と言えます。
わたし自身も①~⑥のすべてをバイジーとして受けた経験はありませんし、現在バイザーとしても実践できてはいません・・・。
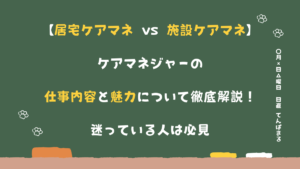
>>ケアマネジャーを目指すべきか迷っている人は必見!ケアマネジャーの仕事内容と魅力について徹底解説
現実で可能な最善策を考える
対人援助職として経験を積んだ役職者や管理者には、バイジーの役割を担うことが期待されます。
しかし管理職として、「管理的機能」を果たすことで精一杯となっていることも少なくないでしょう。
スーパービジョンには「管理的機能」「教育的機能」「支持的機能」の3つがあります。
このなかの「管理的機能」は、バイジーが組織内で適切な役割遂行ができるようにすること」が目的で、「組織のルールや実践の方法をきちんとバイジーに教えること」や「バイジーの生産性と組織の生産性両方のバランスを図ること」といった内容が含まれています。
しかし「管理的機能」に偏ってしまうと、バイジーが援助基盤の応用法を学びながら成長し、仕事に意欲を持ち続けるための「教育的機能」「支持的機能」を果たす時間は取りづらくなります。
また「教育的機能」「支持的機能」の一つである「燃え尽き症候群を予防する効果」も薄れることで、離職に繋がることにもなりかねません。
このような現実問題により、理想のスーパービジョンを実現することは難しいと考えられています。
スーパービジョンで欠かせない要素
たとえスーパービジョンを理想の形で実践できていなくても、「スーパービジョンに不可欠な要素」をしっかりと取り入れることができれば、理想の形に準ずる成果が期待できます。
「スーパービジョンに欠かせない要素」はたくさんありますが、そのなかでも特に重要と言える要素を3つに絞り解説していきます。
- バイザーとバイジーの関係性と契約
- バイザーとバイジーが「共に成長していくプロセス」としての認識
- スーパービジョンにおけるアセスメントに関する話し合いの重要性
1.バイザーとバイジーの関係性と契約
対人援助職が利用者との間で信頼関係を築いていくことが大切なのと同じように、スーパービジョンでもバイザーとバイジー間の関係性は重要です。
バイジーが「わたしのバイザーは信頼できる」と思えていなければ、自分の実践内容を素直に話せません。
では信頼関係に基づく「良い関係」とは、どのようにしたらできるのでしょうか。
バイジーの欠点を指摘するだけでは関係性がぎくしゃくし、バイジーの成長は阻害されてしまいます。
また反対に、称賛し続けるだけではバイジーの成長は止まってしまいます。
そしてバイザー自身の成長も期待できません。
つまり良い関係(適切な関係)とは、「必要な称賛と建設的なフィードバック双方のやり取りができる関係」だと言えるのです。
真の成長を目指している時には、自分の弱さと向き合うことも必要になります。
そして良い関係を保つためには「何を目指してスーパービジョンを行うのか」「スーパービジョンはどのように進められるのか」などに関して、両者の間でルールが合意されていなければいけません。
できれば、契約書のような形にしておくことが望ましいとされています。
スーパービジョンの「契約書に最低限盛り込む内容」は以下の通りです。
- スーパービジョンの方法・回数・時間・必要な準備
- 秘密保持の原則
- スーパービジョンの焦点(何をスーパービジョンで話し合うか)
- お互いに問題を感じた時の「どのようにその問題に対応するのか」に関する問題解決方法
- スーパービジョンの結果にかかる扱われ方(「結果がバイジー評価の対象となるか」ということ)
このような内容の取り決めを文章で交換しておくことによって、期待の不一致やその後の問題を回避することができるといわれています。
逆に契約内容を曖昧にすれば、バイザーとバイジーの「期待・境界・目的」が異なってしまいます。
2.バイザーとバイジーが「共に成長していくプロセス」としての認識
スーパービジョンに関する誤解の一つに「スーパーバイザーは完璧で、すべての答えをもっていなければならない」というものがあるようです。
もちろんバイザーは十分な実践経験があり、教え方・伝え方のバリエーションを含めたスーパービジョン実施に必要不可欠な知識やスキルを持ち、それらをバイジーの力量に合わせて適切に応用する必要があります。
しかしこれは、バイザーが「完璧で必ずいつもバイジーの抱える問題に対する答えをもっている」ということを意味するわけではありません。
スーパービジョンはバイザーとバイジーによる「共同作業」です。
バイジーもバイザーも「共に成長するプロセス」であると認識する必要があります。
つまり「バイジーはバイザーに過剰な期待をしてはいけない」「バイジーもしっかり自分の責任をはたさなければいけない」ということです。
少しくどい言い回しとなりますが、「バイザーはバイジーの成長のためにバイジーが抱えている課題を共に振り返り、問題解決に必要な情報を探求し、解決の道筋にはどのようなものがあるのかについて、いくつかの仮説を考えだす」といった表現が適切かもしれません。
バイザーの成長に必要なこと
わかりやすくするために、「バイザーの成長に必要なこと」を10項目にまとめてみました。
- バイザーとしての自覚を持つ
- 自信を持つ
- 自立性と依存感覚(頼っても良いという感覚)を併せ持つ
- スーパービジョンの方法や手続きを理解し、適切にバイジーの力を見積もることができる
- スーパービジョンの組み立て方(構造)を理解・実施できると同時に、必要に応じて柔軟に実施できるバリエーションを持ち、それらをうまく使える
- バイジーのニーズを大切にしながらも、バイザーとしてのニーズも大切にできる
- バイジーに対して適度な自己投資(時間・エネルギー)ができる
- スーパービジョンにおけるバイジーとの関係性と、スーパービジョンのプロセスの両方を大切にできる
- バイザーとしての自分がスーパービジョンに及ぼす影響に気づき、その評価ができる
- 自分の課題やバイアス・逆転移・関係性を認識し、それらを適切に抑制しながら自分の能力と限界の両方を現実的に見積もることができる
ここで少しだけ、項目ごとのポイントを解説します。
バイザーが専門職としての十分な力量を身につけ、バイザー役が務まる自覚・自信を持ちましょう。
同時に自分に足りないものがあることも自覚し、「ポジティブな意味の他者依存をしてよい」と考えることが必要となります。
つまり「お互いの助け合いが許容できる」ということです。
バイザーが一方的にバイジーの要求を受け入れることだけを目指すのではなく、バイザーとして必要だと感じたことをきちんとスーパービジョンに取り入れる必要があります。
バイジーがサポートしている時にはその支援を惜しみませんが、バイジーが利用者に対して「なすべきこと」ができていない時には、それをきちんと伝えます。
つまり「バイザーとしてのニーズを抑え込まない」ということです。
お互いに素直に話ができる関係性が保てるように留意します。
スーパービジョンで必要な内容が話し合われ、「課題理解と課題を解決する方法」の探求を行っていきます。
つまり「バイジーとの関係性と課題解決に向けたプロセスのどちらか一方に偏らない」ということです。
スーパービジョンの成長を3段階で考える
さらにスーパービジョンには、バイジーの成長段階に合わせて行う必要があります。
なぜならば、バイジーの成長段階によって強調する点が異なるからです。
考えられる「成長段階」は下記の3段階となります。
- 第1段階
- 自分が学んだことをどのように実践の場で使うことができるかわからず、不安を抱えている時期です。
- 職場で必要とされている基本的な「スキルのレベル」や「仕事のパターン」を身につけ、それらを使えるようにしなければいけません。
- このような段階にあるバイジーに対して、バイザーが主に行うことは、「情緒的なサポート」や「日々のサービスに必要な情報の提供」です。
- 第二段階
- この段階では「自立した対人援助者」となる段階です。
- バイザーに依存する割合も少なくなり、バイジーが自分で判断できる領域が増えていきます。
- 第三段階
- 最終段階は「より高いレベルの専門実践ができるような自律性」を獲得した状態です。
「自身の関わるバイジーがどの段階なのか」をイメージすることで、より効果的なスーパービジョンとなるでしょう。
3.スーパービジョンにおけるアセスメントに関する話し合いの重要性
スーパービジョンではバイジーの実践内容について、さまざまな側面から話し合いを行いますが、なかでも「クライエントに何が起きているのか、問題の背景に何があるのかの理解を深めていく」というアセスメントは非常に重要で、比重が大きくなります。
ここでは「アセスメントの役割と内容」と「アセスメントの話し合いで必要なこと」に分けてお伝えします。
アセスメントの役割と内容
アセスメントは対人援助の心臓部分であり、単独で成立するものではありません。
対人援助職がクライエントに対して支援をする際の一部です。
アセスメントのプロセスを通して、信頼される援助的関係の基礎を作るのです。
さらに言うと、アセスメントとは「ただ単にクライエントから情報を入手すること」を意味するのではありません。
「クライエントの抱えている問題解決に役立つような情報を見つけ出すこと」と並行し、「クライエント自身が抱くさまざまな感情を理解すること」に努めます。
そのうえで、「クライエントが置かれている状況をどのようにして改善できるのか」をクライエントと共に真剣に考え、関わっていくプロセス全体がアセスメントなのです。
アセスメントについての話し合いの中で必要なこと
わかりやすくするために、「アセスメントについての話し合いの中で必要なこと」を6項目にまとめてみました。
- クライエントと対人援助職が、どのように関係性を構築しコミュニケーションを図っているのか
- 対人援助職は、どのように情報収集・分析を行っているのか
- それらの情報を使って、どのように支援計画を作っているのか
- どのように支援を実施し、成果を振り返っているのか
- 連携する多職種・他機関と、どのように関係を構築しているのか
- どのようにして支援者が自分の経験を振り返り、学びを得ているのか
ここで注目してほしいのは、「どのように」という「具体性・事実を伴ったプロセス報告」の重要性が協調されているということです。

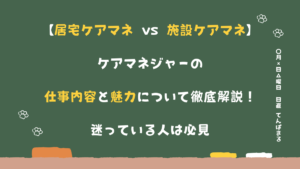
>>ケアマネジャーを目指すべきか迷っている人は必見!ケアマネジャーの仕事内容と魅力について徹底解説
まとめ
「現実的かつ本質を見失わないスーパービジョン」について、理解が深まったでしょうか。
繰り返しになりますが、理想のスーパービジョンを実現することは簡単ではありません。
しかし「スーパービジョンに不可欠な要素」をしっかりと取り入れることができれば、理想の形に準ずる成果が期待できます。
この記事が「みなさんの職場における最善のスーパービジョン」を考えるきっかけとなれば幸いです。
スーパービジョンの質を高め、「対人援助職のエキスパート」になろう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。