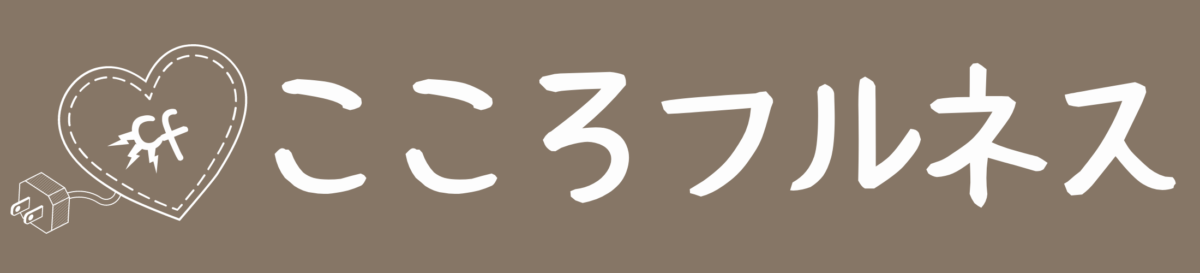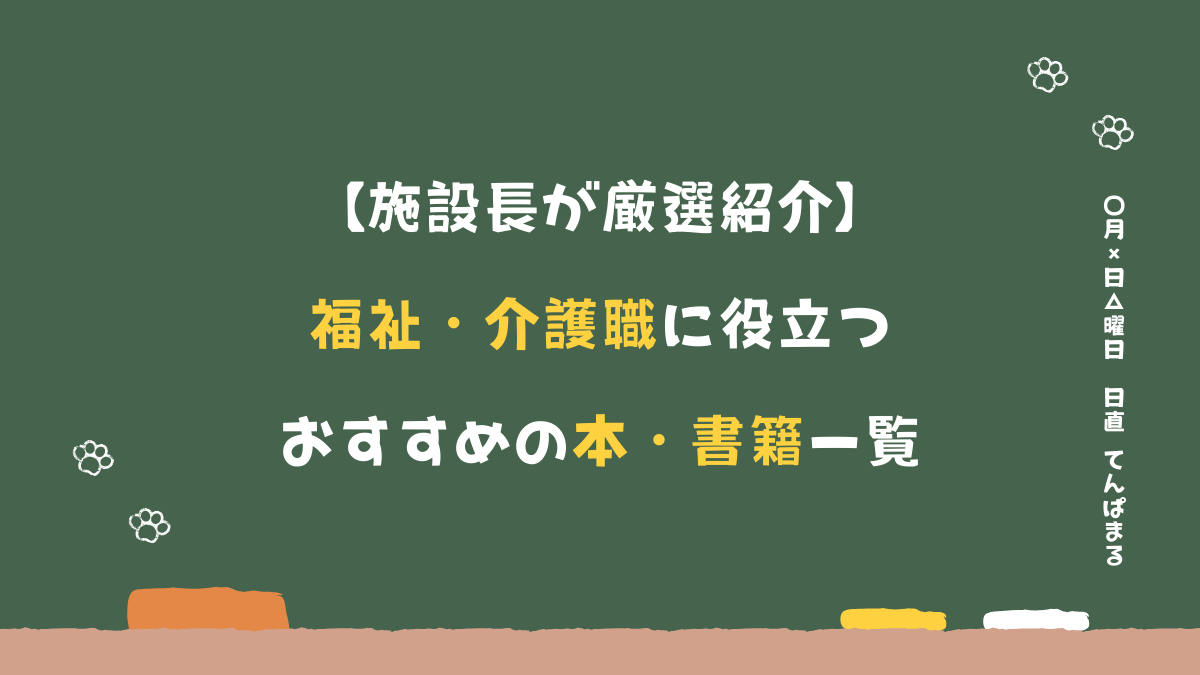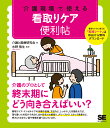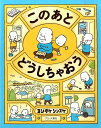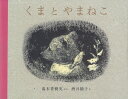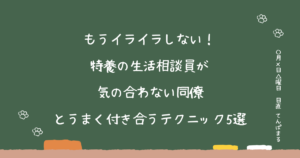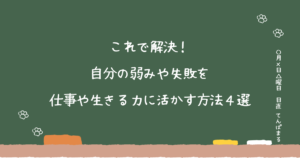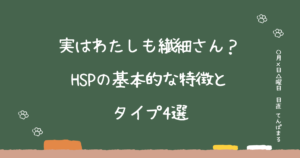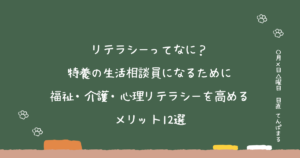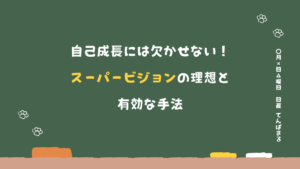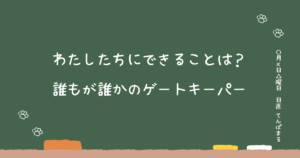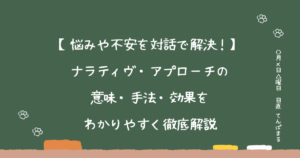本を買って勉強したいと考えているのだけれど、何がおすすめかしら?
どうせ買うなら、失敗したくないわ……。
迷っているなら、まずはぼくが紹介する中から選んでみたら?
どれもためになる、おすすめばかりだよ!
この記事では、福祉・介護職に役立つおすすめの本・書籍をカテゴリー別に厳選紹介!
あなたにも、「これだ」と思える一冊がみつかります。
目次
生活相談員
特養・デイサービスの生活相談員 仕事ハンドブック 役割が見える、業務の進め方がわかる
特養の生活相談員について、どれよりもわかりやすく丁寧に書かれている一冊です。
これから生活相談員を目指す学生や新人には特におすすめ!
実際の仕事内容だけでなく、ソーシャルワーカーとしての心構えまで学ぶことができます。
現場で使えるデイサービス生活相談員便利帖
「デイサービス」の生活相談員に特化して書かれた一冊です。
「特養」と類似する点・違う点を比較することができるため、見る価値アリ!
生活相談員に特化した本は数が少ないから、とても貴重だよ!
ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカーという仕事
それからソーシャルワーカーを目指す学生や新人に、ぜひ読んで欲しい一冊!
初心者向けの内容ですが、何度でも立ち返り、読む価値のある内容です。
ソーシャルワーカー 「身近」を革命する人たち
「そもそもソーシャルワークとは何なのか?」について、丁寧に書かれています。
特養の生活相談員として働くうえでも、知っておくべき内容が満載!
「社会福祉士と精神保健福祉士が一元化されていない理由」についても書かれているため、これから社会福祉士の資格取得を目指す人にはおすすめです。
ソーシャルワーカーのためのアドラー心理学 どうすればクライエントを支援することができるのか
アドラー心理学が好きなぼくにとって、読まずにはいられない一冊です。
ソーシャルワークと心理学の掛け算は、クライエントを支援するときに、大きな力になります。
この本を読むことで「もっと心理学を勉強したい」と思うはず!
ソーシャルワーカーが葛藤を乗り越える10のエッセンス
ソーシャルワーカーは、ジレンマや葛藤を抱えやすい職種。
ストーリーを交えた解説で、とてもわかりやすく書かれています。
「10のエッセンス」は、悩んでいるソーシャルワーカーの現状を打破する助けになるでしょう。
新版 社会人のための社会福祉士 ソーシャルワーカーを目指すあなたへ
社会人学生として、これから社会福祉士を目指す人にスポットライトを当てた本。
「ソーシャルワーク」について、深く考えるきっかけに!
ソーシャルワーカーに必要とされる視点や、目指すべき姿が学べます。
施設長であっても、ソーシャルワーカーであることを意識すべきよね!
リーダーシップ
福祉リーダーの強化書 どうすればぶれない上司・先輩になれるか
ソーシャルワーカーにはリーダーシップ・マネジメント能力が求めらる場面も多い!
本書では「苦手な部下との向き合い方」「注意すべきダメ上司の類型」「磨きをかけるべきチカラ」などが紹介されています。
リーダーシップを発揮したい人だけでなく、すべての福祉職に読んで欲しい!
まさに強化書です!
介護リーダー必読! 元気な職場をつくる、みんなを笑顔にする リーダーシップの極意
介護リーダーは介護業界で誰もが通るキャリアの1つです。
「これから介護リーダーを目指す人」「介護リーダーとして今悩んでいる人」「生活相談員として介護リーダーを支えたい人」におすすめ!
ネガティブな気持ちをポジティブにさせてくれます。
やさしくわかる!すぐに使える!介護施設長&リーダーの教科書
本書の中に「感動ストーリー」はまったく出てきません。
現実的なとてもロジカルな一冊!
身につけるべきスキルと具体的な方法がわかり、施設長となる準備・心構えに繋がります。
リーダーシップを身に着けたいなら、どれも読んでおいて損はナシ!
コミュニケーション力
伝え方が9割
言わずと知れたベストセラー。
特養の生活相談員には、高いコミュニケーションスキルが求められます。
伝え方にはどの分野にも共通するシンプルな技術が!
本書を読んで、クライエントに対し「どのように伝えるべきか」を学びましょう。
対人援助のスキル図鑑 イラストと図解でよくわかる
本書は文章だけでなく、イラストが豊富なところが特徴です。
対人援助職として今すぐ使える「53のスキル」を紹介!
福祉現場の対人援助職、とりわけソーシャルワーカー向けにスキルが整理されています。
超ファシリテーション力
ファシリテーション力は、生活相談員に必要なスキル。
会議が「つまらない・決まらない・終わらない」と課題を感じている人には、特におすすめ!
著者の平石アナはABEMAPraime(アベマプライム)ので司会を務め、個性的な出演者をさばいています。
そのテクニックは、福祉現場でも活かされるものばかりです。
転職・キャリア
転職&天職ハック
仕事には、人生のなかで多くの時間と労力を費やします。
「福祉・介護の仕事は自分に合っているのか?」そう思いながら仕事をしている人も多いはず。
そんな仕事選びでの誤解や思い込みを科学的データに基づき検証し、転職で失敗しないための合理的な選択肢が掛かれています。
鈴木祐さん、大好きです!!!
このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法
「転職したいけど、どうしようかな・・・」と悩んでいる人におすすめ。
(転職する時に大切なには、情報ではなく思考法なのです)
これから転職する人には、絶対に読んで欲しい一冊!
これこそ転職論の決定版です。
ライフキャリア 人生を再設計する魔法のフレームワーク
人生100年時代を意識した、キャリア・生き方について書かれています。
「ワークキャリア」から、個々人の人生全体で見る「ライフキャリア」への激変!
第2・第3の人生を早期にデザインし、準備するための「考え方」と「フレームワーク」をきちんと学べます。
地域・在宅医療
みんなの社会的処方 人のつながりで元気になれる地域をつくる
社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法
「社会的処方」という言葉を知っている人は少ないはず……。
この言葉を知るためだけでも、読む価値があります。
生活相談員が孤立という課題に対し、どのように向き合うべきかについて、考えるきっかけになるでしょう。
在宅医療カレッジ 地域共生社会を支える多職種の学び21講
「在宅医療カレッジ」は、2015年にスタートした医療・介護多職種のための学びのプラットフォームです。
このプラットフォームではトップランナーを「教授」に迎え、定期的なセミナーを開催していました。
本書はその人気セミナーのダイジェスト版です。
在宅医ココキン帖
著者である市橋亮一先生、紅谷浩之先生、竹ノ内盛志先生は3名とも在宅医です。
在宅であっても施設であっても、関わりの勘所と鉄則は変わりません。
福祉・介護職として、実践に活かせる知識ばかりdす。
ACP(人生会議)・デスカフェ
ACP入門 人生会議の始め方ガイド
「ACP(人生会議)とはなんなのか?」について、わかりやすく楽しく解説されています。
ACP(人生会議)の入門書と言っても良いでしょう。
「縁起でもない話」を自然に切り出すための話術が記載!
ACPと切っても切れないお金の話
「ACP(人生会議)どころじゃない」というのが病院のリアル……。
だからこそ、特養(生活の場)でACP(人生会議)を行う意義は大きいと感じます。
利用者の経済状況を無視してはACPは実践できない!
ACP(人生会議)に取り組むスタッフが不都合な真実に真っ向から挑み、その解決策を提案している一冊です。
わたしたちの暮らしにある人生会議
ACP(人生会議)は結果ではなくプロセス。
実際の医療・ケアで起きている物語について、様々な立場(目線)から紹介しています。
ACP(人生会議)を展開するヒントがちりばめられている一冊です。
熱い物語と一緒に、ACP(人生会議)の理解を深めましょう。
ACP人生会議でこころのケア ケアする人、される人、共に死生観・スピリチュアリティの向上をめざして
人生の最終段階において、心のケアを必要とするのは、利用者・家族だけではありません。
ぼくたち専門職もその一人!
医療・心理学の専門的な方法だけではなく、マインドフルネスや臨床瞑想法なども取り入れ、共に癒やし、癒やされるための方策を紹介しているのが本書です。
デスカフェ・ガイド 「場」と「人」と「可能性」
死についてカジュアルに語り合うデスカフェ!
ACP(人生会議)と親和性が高いことも注目されています。
これからの多死社会に向けて、デスカフェの可能性を集約した一冊です。
全国各地で開かれているデスカフェの違いについて、わかりやすくまとめられています。
多死社会を迎える現代において、ACP(人生会議)の概念は必ず深めておくべきね!
看取り
死を前にした人に向き合う心を育てる本 ケアマネジャー・福祉職・すべての援助者に届けたい視点と看取りケア
NHKプロフェッショナル仕事の流儀にも出演した小澤先生の著書!
ぼくたち福祉専門職が看取りを行う際に大切にすべき視点について、わかりやすく載っています。
まさに「心を育てる本」です。
穏やかな死のために
石飛先生は「平穏死」という言葉の先駆者です。
実際に石飛先生の講演を聞いたことがありますが、先生の言葉一つひとつには重みがあり、説得力を感じました。
看取りに携わる人にとって、バイブルとなり得る一冊です。
介護現場で使える 看取りケア便利帖
特養は言わずと知れた「終のすみか」。
けれども、看取りを実践していない施設もまだまだたくさんあるのが実情です……。
本書には「看取りのキホン」が、わかりやすく書かれています。
たんぽぽ先生のおうち看取り 在宅医が伝える、よりよく生ききるためのメッセージ
サブタイトルのとおり、「よりよく生ききるためのメッセージ」が込められています。
住み慣れた自宅で最期を迎えることができることの尊さ。
それがわかる一冊です。
素敵なご臨終 後悔しない、大切な人の送りかた
具体的なケアの技術だけでなく、人生の最終段階に向かって起こる体や心の変化について、丁寧に解説しています。
図解が用いられ、医療用語が多く使われていない点も高評価!
「医師ではないからこそ、できるケアがある」という言葉が刺さります。
いのちをつなぐ看取り援助 特養の介護を支える経営と看護から
特養は介護職のみならず、多職種協働・連携で成り立っています。
生活相談員として知っておくべき「介護の実情」が学べる非常に有益な本です。
経営の視点を交えながら、「看取りとは何か?」を教えてくれます。
看取りは、福祉・介護職として働くうえで必要な知識だよ!
心理学・セラピー
心を壊さない生き方 超ストレス社会を生き抜くメンタルの教科書
「筋トレ最強!!」と謳うtestosterone(テストステロン)さんが超ストレス社会を生き抜くノウハウについて書いています。
筋トレで自己肯定感を爆上げ!
読めば必ず元気が出ます。
嫌われる勇気 自己啓発の源流
言わずと知れた名著。
心理学に携わる人で、この本を読んでいない人はいないでしょうが、それでも紹介せずにいられません。
「承認欲求を否定せよ」「課題の分離」など、アドラーの教えが満載!
悩んだり迷ったときに立ち返るきかっけになる本です。
眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学 集団・社会生活の中の人間の心の本質を探る!
ぼくが「心理学を本格的に学びたい」と思ったきっかけになった本のひとつ!
心理学はあやしいものではなく、身近なものです。
そのなかでも社会心理学は、ソーシャルワークと心理学を掛け合わせたもの。
「へ~」「ほ~」と、楽しく学ぶことができます。
限りなく黒に近いグレーな心理術
あやしい題名からは想像できないロジカルな内容です。
「グレーな心理術」を身に着けることで対話が楽しくなり、相手からも感謝されます。
心理学を生活相談員の仕事に応用してみて!
ナラティヴ・セラピーのダイアログ 他者と紡ぐ治療的会話,その〈言語〉を求めて
対人援助職3名が対話について、様々な視点から読み解いていきます。
カウンセリングの鍵は対話であることを再認識。
「ナラティヴ・セラピー」「ダイアログ」の知識は、福祉・介護職であっても必ず活かされます。
「ナラティヴ・アプローチ」の土台となった心理療法について、理解が深まるでしょう。
はじめての家族療法 クライエントとその関係者を支援するすべての人へ
「公認心理師現任者講習会」で講師を担当していた浅井先生が著者。
同じく講師だった八巻先生が推薦している……。
こんな一方的なご縁を感じているといった理由を差し引いても、読まない理由は見つかりません!
家族療法がどのようなものなのか、わかりやすく丁寧に書かれた一冊です。
心理学の知識は、福祉・介護職として働くうえで役に立つものばかり!
絵本(死について考える)
わすれられないおくりもの
このあとどうしちゃおう
100万回生きたねこ
くまとやまねこ
絵本を用いることで、死についてのハードルが下がるわね!
子どもだけでなく、大人にもおすすめできるわ~。
 まるこ
まるこ