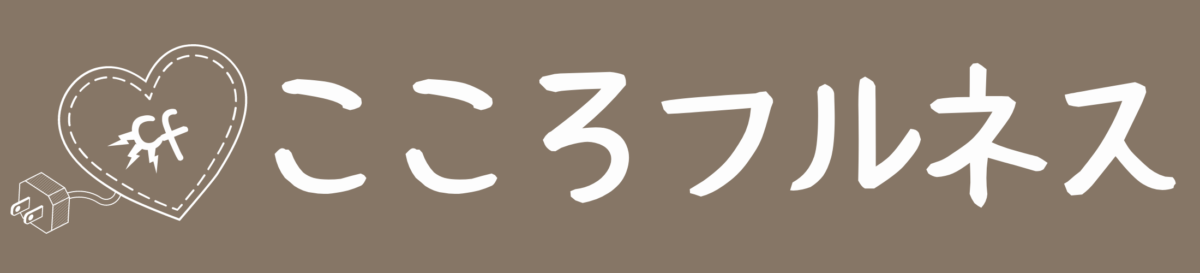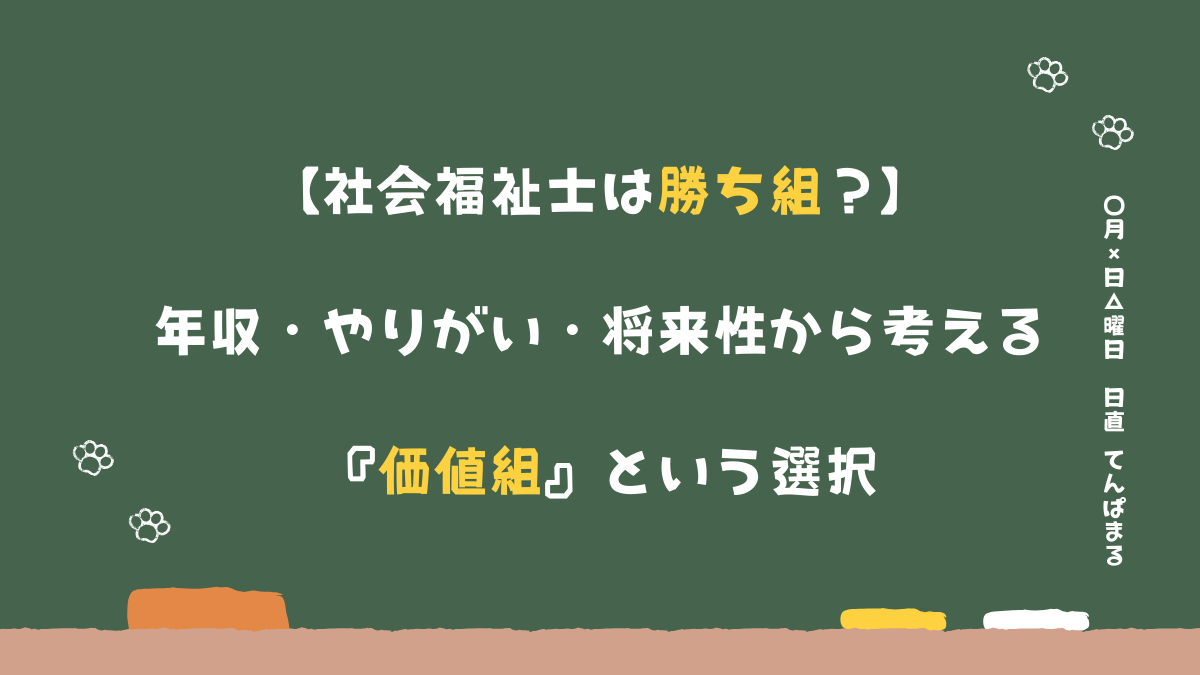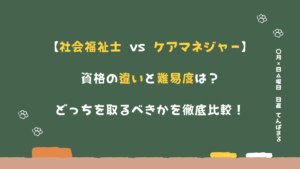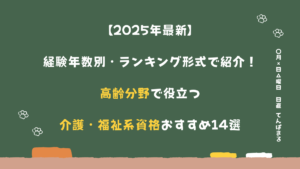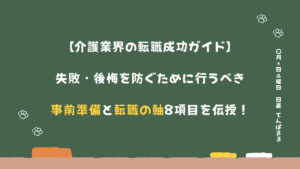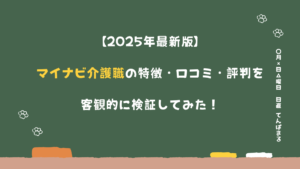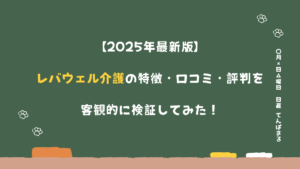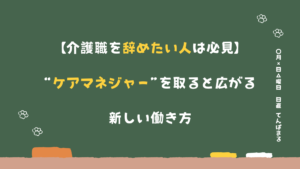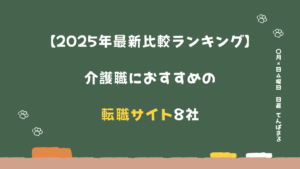まるこ
まるこ社会福祉士が勝ち組と言われることがあるけれど、どうして?



勝ち組と言われる所以(ゆえん)について、お伝えしていくよ!
福祉の道を志す学生や資格取得を目指す同僚(社会人)から、「社会福祉士って、勝ち組じゃない?」こんな話を聞くことがあります。
社会福祉士は国家資格であり、一定の専門性と社会的信用がある職業。
でも、いざ調べてみると「年収が低い」「報われにくい」といったネガティブな印象も目立ちますよね……
この記事では、「勝ち組」という一見派手なイメージではなく、社会福祉士という仕事の「価値」に注目して、年収・将来性・やりがいから総合的に解説していきます。
そして、社会福祉士という仕事を単なる「資格」ではなく、 「生き方」として見つめ直し、「勝ち」よりも「価値」を見出す視点をお届けします。
最後まで、じっくりとご覧ください。
平均年収のリアル
社会福祉士の平均年収
厚生労働省の調査(令和2年度 社会福祉士就労状況調査)によると、 社会福祉士の平均年収は約403万円。
また、国税庁の「民間給与実態統計調査」(令和4年分)では、 民間企業の平均年収は約458万円です。
つまり、数字だけを見れば、社会福祉士は“平均以下”……
- 厚生労働省「社会福祉士就労状況調査」(令和2年度)→ 社会福祉士の平均年収:約403万円
- 国税庁「民間給与実態統計調査」(令和4年分)→ 全国平均年収:約458万円
「福祉はやりがいだけで食べていけない」──そんな声も珍しくありません。
けれども、だからといって「社会福祉士は負け組」と言えるのか……
ぼくはそうは思いません。
なぜなら、目には見えない“価値”を生み出している人が、たくさんいるからです。
分野別の平均年収・待遇
分野別の平均年収・待遇の特徴は下記のとおり。
行政(公務員)の平均年数は、他の分野よりも高めです。
| 分野 | 主な職場例 | 年収の目安 (初任~中堅) | 待遇・特徴 |
|---|---|---|---|
| 医療 | 病院 (急性期、回復期、精神科) | 約350~500万円 | ・MSW(医療ソーシャルワーカー)として勤務 ・入院・退院支援や家族対応が主な仕事 ・夜勤なし ・規模で待遇に差あり |
| 高齢 | 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 地域包括支援センターなど | 約300~450万円 | ・ケアマネジャー、生活相談員(支援相談員)としての勤務 ・ケアプランの作成、入所(退所)支援が主な仕事 ・入所系サービスの介護職と兼務の場合、夜勤がある場合も ・法人の体力次第で待遇に差あり |
| 障害 | 相談支援事業所 障害入所施設 就労支援施設など | 約280~420万円 | ・生活支援員、サービス管理責任者、相談支援専門員として勤務 ・利用者支援、サービス等利用計画の作成が主な仕事 ・入所系サービスの生活支援員の場合、夜勤がある場合も ・法人の体力次第で待遇に差あり |
| 児童 | 児童相談所 児童養護施設 児童発達支援など | 約300~450万円 | ・児童福祉司、児童指導員、児童発達支援管理責任者として勤務 ・心理、教育との連携が必要な仕事 ・児童指導員の場合、夜勤がある場合も ・公務員採用だと安定(民間との待遇差は大きい) |
| 行政 (公務員) | 市役所 福祉事務所 自治体庁舎など | 約350~600万円 | ・地方公務員(福祉職)として勤務 ・年齢、経験で安定した昇給あり ・福利厚生も充実 |
『勝ち組』か否かは、年収・待遇だけで語れるか?
たしかに年収・待遇といった“見える指標”は、生活を成り立たせるうえでとても大切な要素。
特に、家庭を持つ、ローンを組む、老後に備えるといった現実的な課題に向き合う場面では、安定した収入が安心感をもたらします。
しかし、福祉の仕事は“お金”だけでは測れない価値が存在するという点も、決して忘れてはならない重要な視点です。
目の前の誰かの人生に寄り添い、時にはその人の未来を大きく変える支援に繋がる場合も!
このような“人の役に立てた実感”や“ありがとう”という言葉が、日々の業務において大きな原動力になります。
それは給与明細には載らない、「やりがい」「誇り」といった形のない報酬です。
年収・待遇といった数値的な「勝ち負け」とは異なる価値観、「価値組」という視点から、社会福祉士という仕事の魅力を改めて見つめ直すことが求められます。
「勝ち組」ではなく、「価値組」という考え方
「勝ち組」という言葉は、多くの場合、年収・待遇・肩書きといった“見える成果”によって語られます。
しかし、社会福祉士の仕事においては、そうした物差しだけでは測りきれない部分があることを忘れてはいけません。
たとえ平均年収が高くなくても、他者の人生に深く関わり、変化を生み出す力があること……
「価値組」としての社会福祉士の役割
「価値組」とは、社会に対して実質的な価値を提供し、人々から信頼と感謝を受ける存在。
社会福祉士はまさにその代表格です。
現場ではこんな場面があります。
- 高齢者が数年ぶりに外出し、「ありがとう」と涙を流す
- ひきこもりの青年が、自ら語りはじめた瞬間に立ち会う
- 経済的困窮者が支援を受け、自立に向けて再スタートを切る
こうした場面こそ、社会福祉士が“人間力”で価値を生み出している証です。
数字では測れない「価値」をどう育むか
「価値組」としての在り方を貫くには、専門知識だけではなく、以下のような力が必要です。
- 共感力:相手の気持ちに寄り添い、安心感を与える力
- 関係調整力:家族・医療・行政など多方面と連携する力
- 倫理観:誰かの人生に関わる者として、誠実に判断する力
社会福祉士が「価値組」として成長していくためには、日々の支援をただの業務で終わらせず、「この関わりが、どんな価値をもたらすか?」を問い続ける姿勢が大切です。
困っていた人が笑顔を取り戻した時、家族に希望が戻った時、生活が整い自立への一歩がふみだせた時など、数字では測れない変化こそ、社会福祉士としての成果物だと思います。
その瞬間こそが、社会福祉士にとっての「勝ち」であり、収入や肩書きよりも、ずっと大きな「価値」です。
人間力を使って価値を創る
社会的な意義がある仕事に誇りを持ち、他者の人生に影響を与える存在。
それが、「価値組」の社会福祉士です。
- 家族から「ありがとう」と涙で感謝された
- 閉じこもっていた高齢者が、再び外に出るようになった
- 孤立していた人が、地域で安心して暮らせるようになった
こうした変化を生むのは、制度の知識だけではありません。
「人と人をつなぐ力」や「心を動かす力」 が求められます。
社会福祉士は、人間力を使って価値を創る専門職であり、それは、他の仕事にはない大きな魅力です。
やりがいと専門性
ここからは、社会福祉士という仕事の本質に迫り、やりがいと専門性についてさらに掘り下げて考えていきましょう。
制度や数字だけでは見えてこない「人と人との関わり」や「強み」に光を当てていきます。
ソーシャルワークという専門性
国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)が示しているソーシャルワークの定義は、下記のとおりです。
ソーシャルワークは、社会変革と開発、社会的結束、そして人々のエンパワメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問である。
社会正義、人権、集団的責任、そして多様性の尊重という原則に根ざしている。
ソーシャルワークは、社会科学、人文科学、そして先住民の知を基盤にしながら、人と構造の相互作用に働きかけて、生活上の課題に対処し、幸福を向上させる。
この言葉のとおり、社会福祉士はただの支援者ではありません。
社会をより良く変える力をもった存在として、 下記のようにさまざまな分野でその力を発揮しています。
医療・高齢・障害・児童・行政・司法etc
この多様性は社会福祉士の最大の専門性であり、以下のやりがいにも通じてきます。



いわゆる、ジェネラリストってやつだね!



特定の領域に特化するのではなく、幅広い分野に対応できる人材・専門職なのね~
やりがいベスト3
やりがいなくして、この仕事を続けることはできません。
社会福祉士として現場に立っていると、制度の壁や人間関係の難しさ、時には葛藤に直面することも……
けれども、それを乗り越えてなお続けていけるのは、日々の実践のなかで「確かにやりがいを感じられる瞬間」があるからです。
ぼくが現場で実感している社会福祉士のやりがいベスト3は、下記のとおりです。
第1位:利用者の人生に寄り添い、変化を共に喜べる
社会福祉士の最大のやりがいは、やはりクライエントの生活が少しずつ良くなっていく姿を支えられることです。
- 「相談してよかった」と笑顔を見せてもらえたとき
- 支援の積み重ねで利用者が自立に向かって歩み始めたとき
- 家族や地域から「ありがとう」と声をかけられたとき
こうした瞬間は、何ものにも代えがたい達成感を与えてくれます。
小さな一歩の積み重ねが、大きな変化に!!
その過程を共に歩めることが、社会福祉士の原動力になります。
第2位:人と社会をつなぐ「架け橋」になれる
社会福祉士は、個人や家族だけでなく、医療・介護・行政・地域など多様な資源を結びつける役割を担います。
人と制度、人と地域、人と人をつなぐ「架け橋」</strong>としてのやりがいは大きいです。
- 医療と介護・福祉を連携させ、在宅生活を実現できた
- 行政制度を活用して、生活の安定を支えられた
- 地域住民やボランティアと協働し、新しい居場所をつくれた
「つなぐことで人の生活が前進する」──これを体感できるのが、社会福祉士の魅力です。
第3位:社会課題の解決に貢献できる
個人に対する支援にとどまらず、制度や地域づくりに関われるのも社会福祉士ならではのやりがいです。
- 介護・福祉制度の改善に声を届ける
- 権利擁護や成年後見など、社会的弱者を守る仕組みに関わる
- 地域共生社会の実現に向けた活動に参加する
「現場の声を社会に反映できる」という実感は、専門職としての誇りにもつながります。
自分の仕事が目の前の利用者だけでなく、社会全体の変化にも寄与していることを感じられるのは、社会福祉士ならではの大きなやりがいです。
社会的必要性と将来性
社会福祉士は、社会的必要性と将来性が非常に高い職種。
ぼくが考える社会福祉士の社会的必要性と将来性は、下記のとおりです。
高齢化と制度改革における中心的存在
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が加速しています。
2040年には「団塊ジュニア世代」が高齢者の仲間入り。
医療・介護・福祉の需要はこれまで以上に膨らむと予測されています。
制度改革によって福祉の現場は常に変化し続けており、社会福祉士はその最前線で支援を担う中心的存在です。
地域共生社会におけるキーマン
「地域共生社会」の実現が国の大きなテーマになっています。
そこでは、社会福祉士がコーディネーターとして、行政・医療・介護・地域住民・ボランティアを結びつける役割を果たすことが期待されています。
ヤングケアラー問題や8050(9060)問題など、支援ニーズは複雑化……
これらの課題に対応できるのは、制度や地域資源を理解し、人と人とを結びつけられる社会福祉士です。
AIでは代替できない人間力
AIの進歩により、「AIが仕事を奪う時代」と言われています。
しかし社会福祉士の仕事には、AIでは代替できない領域が多くあります。
- 感情に寄り添う(共感力)
- 価値観の違いを乗り越える(調整力)
- 倫理的判断が求められる場面(決断力)
- 多職種をつなぐ(ハブとなる力)
たとえば、延命治療を望まない高齢者と、その家族の間に立ち、お互いの気持ちを整理しながら最善の方向性を探っていく……
こうした支援は、マニュアルやAIでは置き換えることができません。
つまり、社会福祉士はこれからのAI時代においても必要とされ続ける職業だと言えます。
「価値組」になるための実践
では、どうすれば「価値組の社会福祉士」になれるのでしょうか?
ここでは、ぼく自身や尊敬する先輩の実践から、3つのポイントをお伝えします。
- ソーシャルワークを楽しむ
- 学び続ける姿勢をもつ
- 発信する・つながる
ソーシャルワークを楽しむ
楽しそうに仕事をしている社会福祉士は、不思議とまわりの人まで元気にします。
「どう支援すればその人がより生きやすくなるか」を考えるプロセスそのものが、人生に寄り添う喜びにつながっているからです。
実習やボランティアで「楽しい」と感じた瞬間を大切にしてほしい……
援対象者と一緒に笑える関係を築くことが、社会福祉士としての大きな原動力になります。
学び続ける姿勢をもつ
福祉の現場は、常に変化しています。
制度改正や新しい支援方法が次々と登場するなかで、知識を常にアップデートし続ける姿勢はとても重要!
だからこそ、学びに終わりはありません。
認定ソーシャルワーカーや精神保健福祉士といった資格を取得し、専門性をさらに深めることで、現場での影響力も高まります。
それは単なる肩書きではなく、支援の質を高める確かな力になるはず!
これからは「価値あるソーシャルワーク」を行う人ほど、収入の面でも正当に評価される時代がやってくると、ぼくは信じています。
発信する、つながる
SNSやブログで学びを言語化し、共有することで、あなたの価値はさらに広がります。
「孤独な専門職」から抜け出し、「仲間とともに成長する支援者」に変化できれば怖いものナシ!
ブログやSNSを通じて自分の考えを発信することは、それ自体が価値ある実践です。
同じ志をもつ仲間とつながることで、新たな視点や支援の形が生まれ、仕事の幅も大きく広がっていきます。
【まとめ】社会福祉士は「価値組=勝ち組」として輝ける!
社会福祉士に求められる役割や責任は、どの業種にも負けないほど大きいものです。
「価値組」としての生き方を貫くことで、結果としての「勝ち」も自然とついてくる!
誰かの人生を支えた分だけ、あなた自身の人生にも意味と誇りが積み重なり、その積み重ねがやがて「本当の勝ち組」への道を照らしてくれるはずです。
社会福祉士は、勝つための仕事ではなく、価値を届けるための仕事!
今日も誰かの心にそっと灯をともす──
その姿勢を持ち続けることこそ、これからの時代における「本当の勝ち組」なのかもしれません。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。